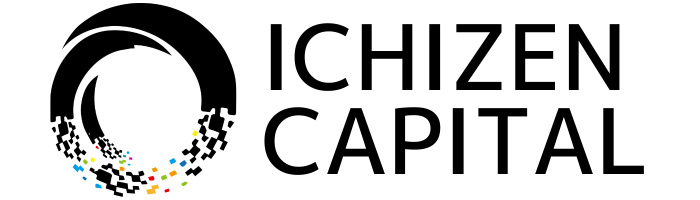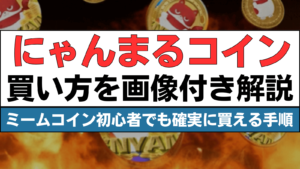仮想通貨USDT(テザーコイン)とは?特徴・税金・テザー問題を徹底解説
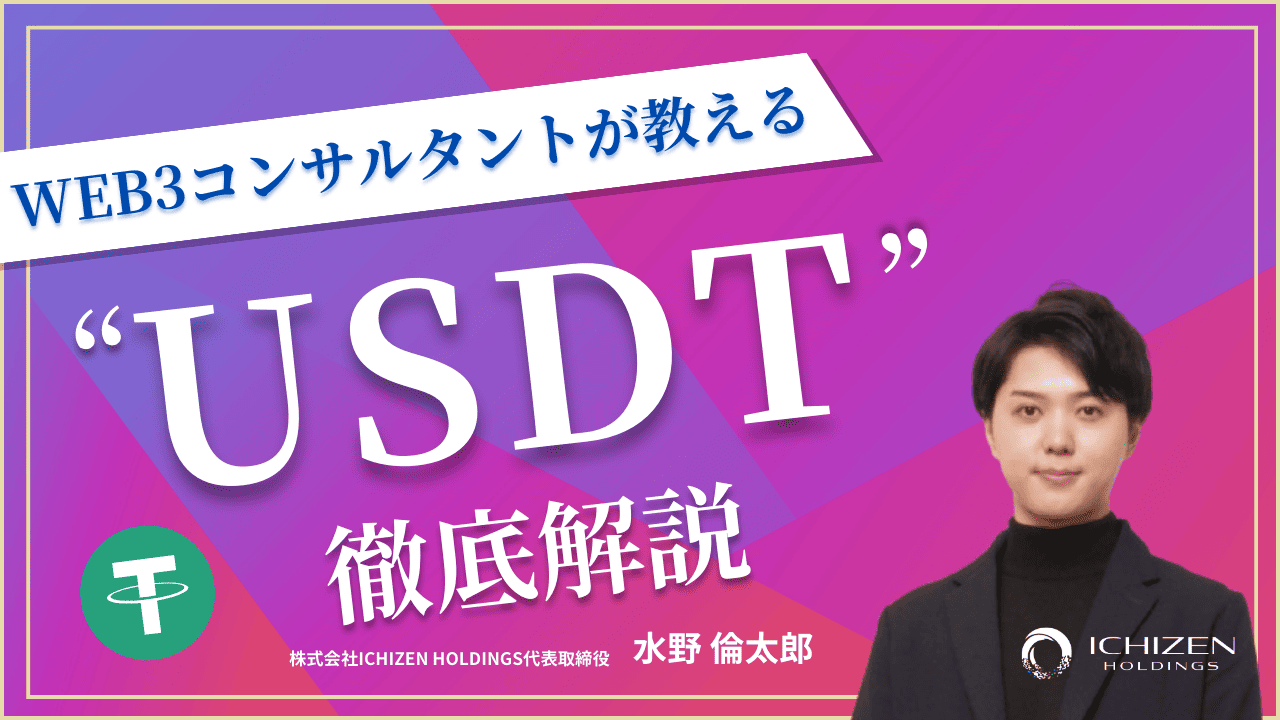
本記事の要約
- USDTとは、米ドル(USD)の価格と1:1でペッグ(固定)されている暗号資産、ステーブルコインと呼ばれる種類の通貨。
- 米ドルが150円の時、USDTも150円となる。(正確には限りなく近い状態)
- 発行元はTether Limited。USDTを発行する場合は発行額と同額の現金や資産を担保に発行している。
- 2017年頃から担保不足を疑われ続けていたが、今は米国債や現金等のポートフォリオを公開している。
- 本当のポートフォリオかという透明性に関する点で懐疑的に思う人がいる。
- 需要と供給をTether Limitedがコントロールすることで、米ドルとの価格を1:1でペッグしている。
- 発行:Tether社が投資家から米ドルや資産等を受け取り、それと同額のUSDTを発行して送付する。
- 償還:投資家がTether社にUSDTを返却し、同社が償還(バーン)する。発行時に受け取った担保を返却する。
- USDTは仮想通貨の中で時価総額4位に位置しており、海外取引所の基軸通貨として広く流通している。
取引ペアのほとんどがUSDTペアで取り扱われている。- ステーブルコインの中で一番流通しており、とりあえずUSDTといった具合で使用する人も多い。
- Tether社が償還・発行できなくなった時点でペグが外れ、仮想通貨市場全体に大きな影響を及ぼす可能性がある。
USDT(テザー)は、「信用できるのか?」という点が常に議論の的になっているステーブルコインだが、ICHIZEN Capitalとしては「リスクはあるが、使われ続けるだろう」というスタンスだ。
「使われている限り潰れない」理論
これまで数々のFUD(不安・不確実性・疑念)があったが、USDTはしぶとく生き残ってきた。仮に完全裏付けがないとしても、「みんなが信じて使っている」限り、その価値は維持されるという実績がある。
結論として、USDTはリスクはあるが、現時点では代替がないため使われ続ける。
ただし、「全資産をUSDTに突っ込む」みたいなことは絶対にやめたほうがいい。BTCやETHと分散しながら、USDCやDAIなどの他のステーブルコインも組み合わせるのがベターな戦略だ。
以下の情報を知りたい人は最後まで読むことをおすすめ

監修 水野 倫太郎
株式会社ICHIZEN HOLDINGS 代表取締役
慶應義塾大学経済学部。2017年米国留学時にブロックチェーンと出会い、Web3の業界に足を踏み入れる。2018年には、日本有数の仮想通貨メディアCoinOtakuに入社。2019年には同社のCMOに就任し、2020年に東証二部上場企業とM&Aを行い、様々なクリプト事業を展開する。2022年に現在代表取締役社長を務めるICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ様々なWeb3事業を手がける。複数のWeb3系事業に出資を行いながら有識者として活動。
USDTとは?基本情報を表で解説
まずはUSDTの概要を把握しましょう。以下のテーブルに基礎データをまとめました。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 通貨名 | Tether(テザー) |
| ティッカーシンボル | USDT |
| 発行元 | Tether Limited(香港拠点) |
| 発行開始 | 2014年(2015年から本格流通) |
| 時価総額 | 約8〜10兆円規模(変動あり、暗号資産トップクラス) |
| ペッグ対象 | 米ドル(1 USDT = 1 USD) |
| 対応チェーン | イーサリアム(ERC-20)、トロン(TRC-20)、Omni Layer、EOSなど |
USDTの基本スペック
USDTは米ドルとの連動を目指すステーブルコインであり、発行元のTether社が現金や短期国債などの準備資産を保有することによって、1USDT=1米ドルという価値を維持する仕組みを採用しています。
こうした法定通貨担保型のステーブルコインとしては最も歴史が長く、幅広い取引所やウォレットで利用されている点が特徴です。
また、イーサリアム・トロンなど複数のブロックチェーンに対応しているため、送金手数料や処理速度、利用できるサービスの幅が広いことも大きな強みとなっています。
現状の時価総額
USDTはステーブルコインとして世界最大規模の時価総額を誇ります。
暗号資産全体でもビットコイン(BTC)・イーサリアム(ETH)に次いで3位前後のポジションを維持しており、多くのトレーダーや投資家にとって欠かせない存在です。
時価総額が大きいほど取引量も多く、市場での流動性が高まりやすい傾向があります。
そのため、USDTは他のアルトコインを購入する際の“受け皿”として利用されやすく、仮想通貨市場のインフラ的な役割を果たしています。
対応チェーン・コントラクト情報
USDTは一つのブロックチェーンに限定せず、イーサリアム上のERC-20トークンやトロン上のTRC-20トークンなど、複数のチェーンで発行されています。
これにより、送金速度や手数料の面で好みのネットワークを選択できる利便性が生まれます。
しかし、送金先のチェーンを誤ると資産を失うリスクがあるため、コントラクトアドレスや送金先の対応ネットワークを正確に確認することが重要です。
大手取引所は大抵の場合、イーサリアム版とトロン版の両方に対応しているため、自分が利用するサービスとの互換性をチェックしておきましょう。
USDTとUSDの違い
USDTは「1 USDT = 1米ドル」を目指して設計されていますが、米ドルそのものではありません。
大まかな機能や価値の連動性は同じでも、根本的な仕組みは大きく異なる部分があります。
法定通貨と暗号資産の境界線
米ドルは米国政府が法的に管理する法定通貨ですが、USDTは民間企業であるTether社が運営する暗号資産です。
価値を担保する手段として米ドルや米国債を保有しているとされますが、公的な中央銀行が保証しているわけではなく、Tether社の健全性や財務開示に依存する点は明確に区別しておく必要があります。
反面、ブロックチェーン上で取り扱えるため、銀行を通さずに手早く安価な国際送金ができるメリットもあります。
法定通貨にはないスピードやグローバルなアクセスのしやすさが、USDTをはじめとするステーブルコインの大きな利点です。
円換金の際の注意点
USDTを円に直接両替できる取引所は日本国内ではほとんど存在しません。
そのため、円でUSDTを入手・換金する際は、国内取引所でビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などを購入し、海外取引所に送金してUSDTに交換するという手順が一般的です。
結果的に複数の取引手数料や為替リスクが発生する可能性があります。
また、「USDT=ドルである」と考えていた場合に円転時のプロセスが想定と異なることもあるので、あくまでも暗号資産として扱う点を意識することが大切です。
テザー社の担保問題とUSDTの発行方法
USDTが「1USDT=1米ドル」という価値を維持できる背景には、発行元であるテザー社(Tether Limited)が米ドルや米国債などの準備資産を保有していることが大前提としてあります。テザー社は、需要に応じて新規発行(ミント)と償還(バーン)を行い、USDTの供給量を調整しています。
しかし過去には、「発行済みのUSDTと同額の資産を本当に保有しているのか」という疑念が何度も市場で取り沙汰されてきました。
2017年頃からは準備資産の開示が不透明であるという批判が強まり、実際に規制当局とのやり取りや訴訟に発展した事例もあります。
近年になってテザー社は外部監査レポートを公表するなど透明性の改善に取り組み、米国債や現金等を中心としたポートフォリオを定期的に報告する姿勢を見せていますが、それでも「正確な資産状況をすべて公開しているのか」という懐疑的な意見は根強く残っています。
新規のUSDTが発行される仕組みは、主にテザー社が顧客(大口投資家など)から米ドルを受け取り、その額に見合うだけのUSDTをブロックチェーン上にミントして顧客に渡す流れで成立します。
逆に顧客がUSDTをテザー社に返却すると、対応する分のUSDTが焼却(バーン)され、そのぶん流通量が減少します。この一連の仕組みが、1USDT=1米ドルというペッグを成り立たせる根幹といえるでしょう。
ただし、最終的にこれを完全に信頼するかどうかはテザー社の透明性や財務健全性に左右されるため、USDT保有者は定期的に監査レポートの更新情報をチェックすることが推奨されます。
USDTと他の米ドルステーブルコインとの違い
USDT以外にも、USDCやDAI、BUSDといった米ドルに連動したステーブルコインが存在します。
いずれも「1ドル相当」を目指す仕組みは同じですが、発行主体や担保方法、規制対応の方針に違いがあるため、ユーザーはそれぞれの特性を比較検討する必要があります。
ステーブルコインの分類とUSDTの位置づけ
一般的に、ステーブルコインは以下の3つに大別されます。
- 法定通貨担保型
法定通貨や政府保証のある金融商品(米国債など)を裏付け資産とするタイプで、USDTやUSDC、BUSDなどが代表的な例です。中央管理者が「準備資産をきちんと保有している」という信頼を得ることで、1トークン=1ドル(など)を維持しています。 - 暗号資産担保型
イーサリアムやビットコインなど、別の暗号資産を担保とする方式で、MakerDAOのDAIがその代表です。担保とする暗号資産が大きく値下がりするとペッグが崩れるリスクがありますが、法定通貨に依存しない分散型の特徴を持ちます。 - アルゴリズム型(無担保型)
特定の担保資産を直接保有せず、価格維持のためのアルゴリズムを使ってトークン供給量を自動調整する仕組みのステーブルコインです。かつてTerraUSD(UST)が代表例として挙げられましたが、2022年5月に大幅なペッグ崩壊を起こしたことで、その脆弱性が露呈しました。
この中でUSDTは**「法定通貨担保型」**に当てはまるステーブルコインです。発行元のテザー社が現金や米国債などの資産を裏付けにしている点が最大の特徴であり、ユーザーとしては「中央管理者の信用力」に最も大きく依存する仕組みといえます。
もしテザー社が十分な資産を持っていないと疑われる事態に陥れば、1USDT=1米ドルという構図が崩れかねないため、透明性や財務情報の開示が極めて重要視されるのです。
中央集権型/分散型ステーブルコインの特徴
ステーブルコインは大きく分けると、USDTやUSDCのような「中央集権型」と、DAIのような「分散型」に分類されます。中央集権型は明確な企業や組織が発行元となり、法定通貨を裏付けとした運用を行うため価格安定性が高いのが特徴です。
一方、分散型は特定の企業に頼らず、スマートコントラクトを通じた自律的な運用が行われますが、担保となる暗号資産の価格暴落時にペッグが崩れるリスクもはらんでいます。
どちらを選ぶかは、ユーザーが重視するポイント(透明性、安定性、規制面、分散性など)によって変わるでしょう。
USDTを日本人が保有するメリット
USDTは暗号資産のボラティリティを緩和しつつ、ドル建て資産を手軽に保有できる点で日本人ユーザーにも魅力的な選択肢となります。
メリット①為替リスク分散
1USDTを1ドル相当として考えれば、円安局面でドル資産を持つのと似た効果が期待できます。
日本円ベースの資産しか持っていないと、世界経済の動向や円相場の変化によって資産価値が目減りするリスクが高まりますが、USDTを保有しておけばある程度リスクを分散できる可能性があります。
また、ビットコインなど価格変動の激しい暗号資産から一旦USDTに逃げることで、相場急落時のショックを回避しやすくなる点もステーブルコインの利点です。
メリット②海外取引所での基軸通貨としての利便性
世界最大級の取引所であるBinanceやBybitをはじめ、海外ではUSDTが基軸通貨として幅広い暗号資産取引ペアに採用されています。
そのため、USDTを一度手に入れてしまえば、グローバルに多種多様なトークンやアルトコインを円滑に取引できるようになります。日本円とのペアが存在しないマイナー通貨でも、USDT建ての市場で手軽に参入可能です。
メリット③DeFiやレンディングなど運用手段が豊富
USDTはステーブルコインであるため、価格変動リスクが小さいという安心感があります。
その特徴を活かして、DeFi(分散型金融)におけるレンディングや流動性プールへの提供など、比較的安定した利回りを狙う運用が可能です。他の価格変動の大きい暗号資産を預けるよりもリスク管理をしやすく、資産を安全に増やしたい投資家にとって選択肢が広がります。
USDTを日本人が保有するデメリット
利便性が高いUSDTですが、法定通貨とは異なるリスクや注意点が存在します。日本の法制度や海外取引所の規制状況も踏まえて理解しましょう。
デメリット①Tether社への信用リスク
USDTの裏付け資産を管理するTether社は民間企業であり、政府のように公的な信用を背負っているわけではありません。
過去には準備資産の開示が不十分であるとの批判や、親会社のBitfinexとの関係が不透明だという指摘があり、市場関係者から疑念を向けられる場面もありました。
現在では外部監査を行うなど透明性向上の努力が見られますが、利用者は企業の財務健全性に依存している点を理解しておく必要があります。
デメリット②国内取引所未対応・購入ハードル
日本国内の仮想通貨取引所では、USDTなどの海外発行ステーブルコインを直接取り扱っていないケースが大半です。
結果的に、日本円で直接USDTを購入できず、まず国内取引所でBTCやETHを手に入れ、それを海外取引所へ送金してUSDTを交換するというプロセスが必要になります。
時間や手間、手数料がかかるうえ、送金ミスによるリスクもあるため、初心者にはやや敷居が高い方法です。
デメリット③各国規制の影響
各国政府がステーブルコインに対してどのような規制を敷くかは、常に大きな不確定要素です。
例えば、米国やEUなど主要国が、ステーブルコインの発行や流通に厳格なライセンス制を導入した場合、Tether社の事業に影響が及び、USDTの流動性が一時的に低下する可能性も考えられます。
日本でも2023年に改正資金決済法が施行され、海外発行ステーブルコインの扱いに一定の制限がかかりました。こうした規制動向を随時ウォッチしつつ、リスク管理を徹底する必要があります。
USDTの将来性
USDTは暗号資産市場で非常に大きな存在ですが、今後の展開は世界経済や法規制の状況、そして暗号資産業界の動向によって大きく左右される可能性があります。
想定シナリオ①:国際的な決済・送金インフラとしての成長
ブロックチェーン技術の進化により、個人間送金や国際決済のハードルは大幅に下がっています。
USDTが安定価値を提供する決済手段として普及すれば、銀行を介さない高速・低コストの送金ネットワークとして新興国や越境ECなどの領域で需要がさらに増すかもしれません。
想定シナリオ②:他ステーブルコインとの競争・棲み分け
USDTは現状、時価総額や流通量でトップを走っていますが、USDCやDAIなど有力なステーブルコインとの競争がますます激化する見通しです。
特に米国の金融規制当局の動向によっては、透明性やコンプライアンス面で有利なUSDCがシェアを伸ばす可能性もあります。また、分散型ステーブルコインが台頭すれば、中央管理型のUSDTは新たな付加価値を打ち出す必要に迫られるかもしれません。
想定シナリオ③:規制強化と透明性の課題
ステーブルコインの安定運用を求める声が高まる一方で、監査や準備資産の開示に関する要件が各国で強化される可能性があります。
もしTether社が各地域の規制要件に迅速に対応できなければ、特定地域でのサービス停止や制限を余儀なくされる事態もあり得るでしょう。
逆に言えば、ルール作りが進んでステーブルコインに明確な法的地位が与えられれば、従来よりも多くの企業・投資家が安心して利用できる環境が整うと期待されています。
USDTの購入方法
日本国内の取引所で直接USDTを買えるケースがほぼないため、現状では海外取引所を活用するのが一般的です。ここでは代表的な方法と注意点をまとめます。
最も効率的な購入手順
USDTを入手するには、まず国内取引所で日本円をビットコイン(BTC)かイーサリアム(ETH)などの主要暗号資産に交換し、それを海外取引所へ送金してからUSDTに両替するというフローが定番です。
BinanceやBybitなど、USDTの取引ペアが豊富な海外取引所を選べば、追加のアルトコインを購入したり、DeFi関連サービスを利用したりする際もスムーズに進められます。
送金にかかる手数料やレートを比較し、安価かつ安全なネットワーク(ERC-20やTRC-20など)を選択すると良いでしょう。
P2P取引・クレジットカードなどの代替手段
海外取引所によっては、P2P取引機能を介して個人間で日本円とUSDTを直接やり取りできる仕組みを提供している場合があります。
また、クレジットカードでUSDTを直接購入できるサービスも存在しますが、為替レートやクレジットカードの手数料が割高になる可能性があるため、慎重に比較検討する必要があります。
購入時の注意点
USDTへの交換時には、送金手数料や為替手数料が複数回発生するケースがあります。
例えば、国内取引所でのBTC購入、BTC送金、海外取引所でのUSDT交換、さらに日本円へ戻す場合は、各ステップで費用やレート差が生じる仕組みです。
また、大きな資産を長期間取引所に預けっぱなしにすると、ハッキングや倒産によるリスクにさらされる恐れがあります。
可能であれば、ハードウェアウォレットや安全な管理環境を用意し、自分だけの秘密鍵で資産を保管することが望ましいでしょう。
まとめ:USDTは仮想通貨市場の「ドル」
USDTは米ドルの価値に連動するよう設計されたステーブルコインで、暗号資産市場のなかでは「ドル」のような立ち位置を確立しています。高い流動性と複数のブロックチェーン対応による利便性、そして価格安定性が魅力ですが、一方で法定通貨ではなく民間企業による発行であるため、Tether社の信用リスクや法規制の影響を常に注視する必要があります。
日本国内からUSDTを取得する際は、海外取引所の利用を前提とした手間やコストがかかる場合が多いものの、国際的な取引やDeFi運用で得られるメリットは大きいといえます。今後は各国の法整備が進むことでステーブルコインの透明性が高まり、より多くの投資家がUSDTなどを活用できる可能性が見込まれます。安定性と利便性を兼ね備えたUSDTを、ぜひ正しく理解して上手に活用してみてください。